グランビルの法則

チャートを勉強する上で、必ず出てくる法則の一つ、グランビルの法則について話します。
とてもシンプルな法則です。
それゆえに、使いこなすにはスキルが必要です。
シンプルなものほど、深さがあるものです。
このグランビルの法則も、その一つてはと感じさせる部分が多々あります。
何故に、深いのか、そして実践で使えるのかなど考察してみました。
グランビルの法則という法則
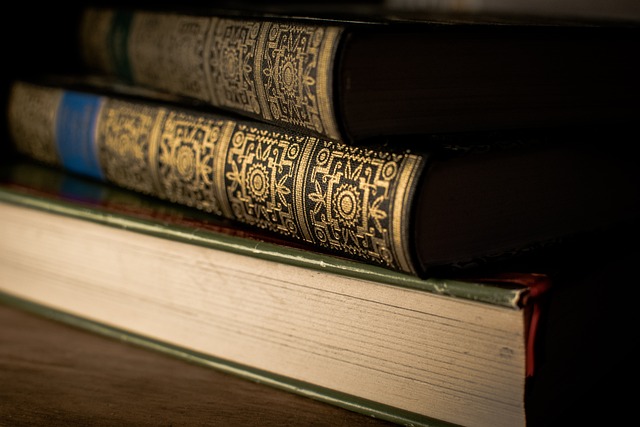
法則とは、
ある現象とある現象の関係を示す言葉である。
また、英語では 「Law」と言い、置く、整えるという意味があります。
神によって置かれたもの、整えられたことという意味もあります。
ウィキペディア
まず、法則という意味からいうと、ある現象がある時、ある現象があるということですね。
グランビルの法則の場合は、一般的には日足と200MA(200移動平均線、以下MA) の関係性についての法則です。
現在は、さまざまなトレーダーたちによって、バリエーションが生まれているようです。
次の図をご覧ください。

グランビルの法則では、200MAに対して、図のようにチャートが動くという法則です。
そして、①〜⑧の売買ポイントがあるというものです。
①から順に説明すると、次のようになります。
【買いのサイン】
| NO | 条件 |
| ① | 移動平均線が下落後、横ばい、または上向きに転じたときに価格が移動平均線を下から上に突き抜けた場合 |
| ② | 移動平均線が上向きの時に、一旦価格は下落し移動平均線を下回るも再度上昇し移動平均線を下から上に突き抜けた場合 |
| ③ | 移動平均線が上向きの時に、一旦価格は移動平均線の手前まで下落するも移動平均線を下抜けることなく再度価格が上昇する場合 |
| ④ | 価格が移動平均線の下に大きく乖離した場合 |
【売りのサイン】
| NO | 条件 |
| ⑤ | 移動平均線が上昇後、横ばい、または下向きに転じたときに価格が移動平均線を上から下に抜けた場合 |
| ⑥ | 移動平均線が下向きの時に、一旦価格が大きく下落し再度上昇し移動平均線を上抜けした場合 |
| ⑦ | 移動平均線が下向きの時に、一旦価格が上昇するも移動平均線の手前で止まり再度下落した場合 |
| ⑧ | 価格が移動平均線の上に大きく乖離した場合 |
これが、グランビルの法則です。
ジョセフ・グランビル氏とは
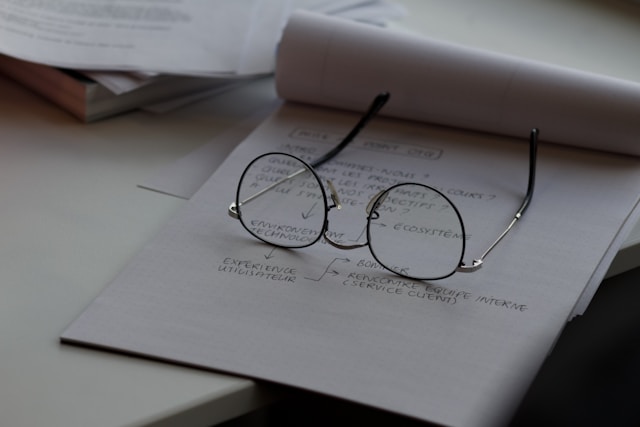
ジョセフ・エンサイン・グランビル、1923年8月20日生まれ。
2013年9月7日、90歳で亡くなりました。
金融ライター、投資セミナーの講演者であったグランビル氏は、投資家としてでなく、アナリストとして活躍していました。
またグランビル氏は、偉大なショーマンとしても知られていたようです。
投資カンファレンスで、棺桶から登場したり、顧客に会う時、プールの水上を歩いてみせたりしたことでも、有名です。
このように、プロモートにも長けていたように思います。
そして最も有名なものとして、グランビルの法則が存在します。
グランビルの法則は使えるのか

冒頭にグランビルの法則は、シンプルが故に、奥が深いと話しました。
実はこの法則がチャートにハマる瞬間を捉えるのは、とても難しいです。
移動平均線とローソク足の動きだけに注意し、トレードしてうまく行けば、だれしもが利益を出してるはずです。
しかし、チャートもまたシンプルが故に、奥が深いのです。
グランビルの法則を実践で使うのなら、判断材料はもっと必要です。
複合的にみて、環境認識ができなければグランビルの法則は活用できません。
ここからは持論になります。
グランビルの法則は、トレード後にチャートを見た時、「あっ、これってグランビルの法則に当てはまるなぁ」という感じです。
エリオット波動の推進波が、ちょうどグランビルの法則のように動くかなぁと感じます。
なので、チャート上に現れる、法則、パターンとしてグランビルの法則を認識すればいいのでは思います。
測らずもこのグランビルの法則や、ダウ理論をさらにバージョンアップしたものに、エリオット波動原理が存在しているという認識をしてます。
エリオット波動原理は、より詳細なルールや波形の見方があります。
さらには、フィボナッチ数列を用いて、宇宙感というか自然の理のようなものにまで及んでます。
このように、 グランビルの法則のみを活用するのではなく、チャートの動向の側面として認識すればいいのではと思います。
まちめ

相場の世界には、先人たちの知恵が理論や原理として存在します。
これらは、チャートを知る上で、とても重要なファクターです。
グランビルの法則もまた、チャートを理解する上で、重要なヒントを与えてくれます。
一見すると、法則性もない流れに見えるチャートでも、一本の移動平均線を引くことで、あたかも法則が存在するように見えてくるから不思議です。
チャートの先には、必ず人が存在します。
その人の集団心理がチャート上に、現れます。
チャートと向き合い、この集団心理を読み解いていくのは、なかなか奥深いものです。
それ故に、いまだにその好奇心が飽きることなく、チャートに向き合うことができます。
壮大なチャートの側面として、グランビルの法則も念頭に置いて、チャートの分析をしていってはいかがでしょうか。
今回は、グランビルの法則について、話しました。







